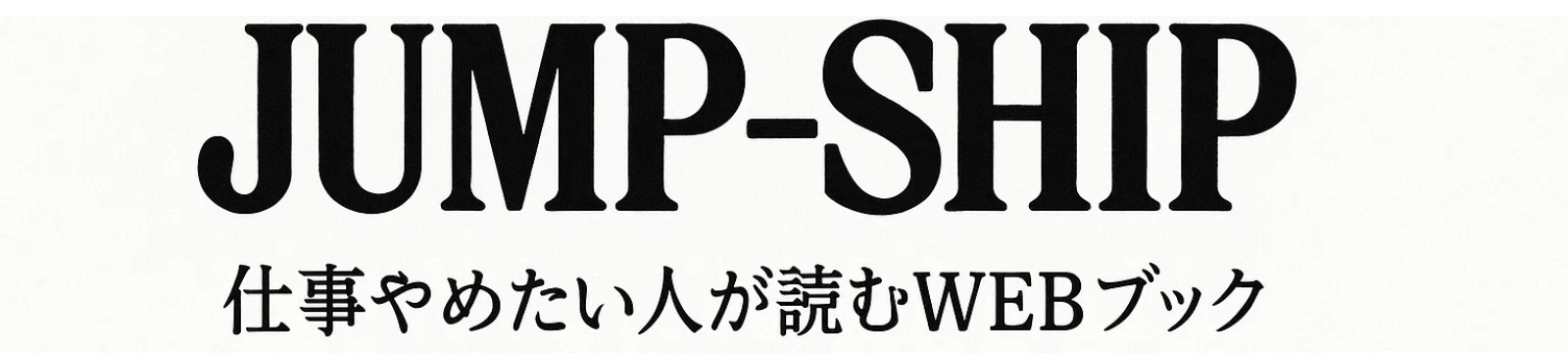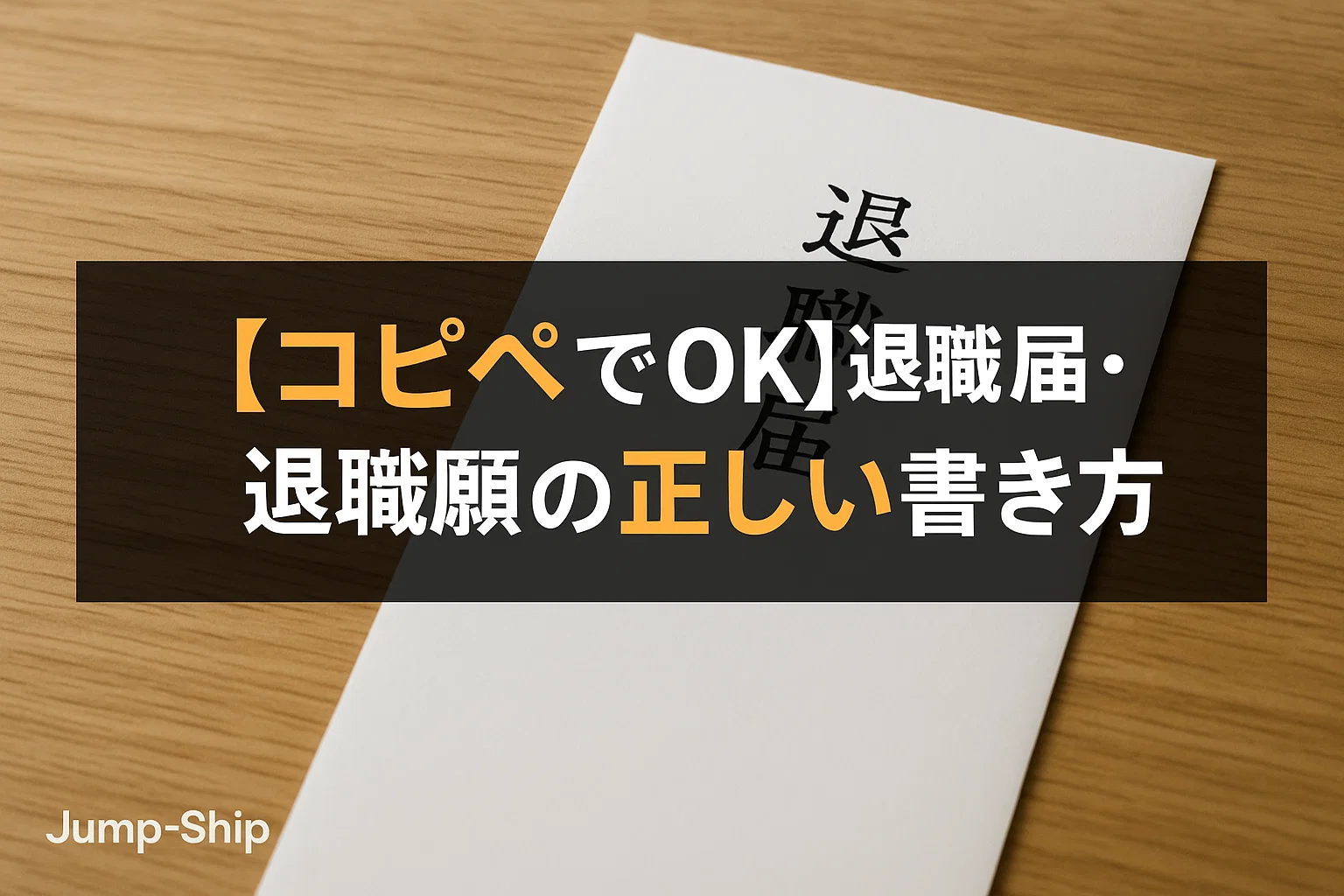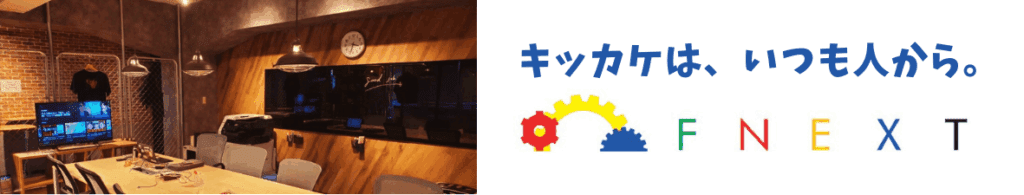退職届や退職願の書き方がわからずお困りですね。正しい書類を作成する最重要ポイントは、「決められたフォーマットに従い、余計なことは書かず、簡潔に事実のみを記載する」ことです。退職理由は「一身上の都合」とし、退職日と提出日、自分の所属と氏名を明記すれば、法的に有効な書類は完成します。この記事では、あなたが今すぐ使える無料テンプレートを複数用意し、書き方の全手順を図解で、封筒の入れ方まで完璧に解説します。
この記事のポイント
- 「退職願」と「退職届」は別物:「願」は退職のお願い(合意前)、「届」は退職の届け出(合意後)です
- 準備物はシンプル:白い便箋(A4 or B5)、黒いペン、白い封筒があればOKです
- 理由は「一身上の都合」一択:具体的な理由を書く必要は一切ありません
- テンプレート活用が確実:この記事のコピペで使えるテンプレートを使えば、誰でも間違いなく作成できます
- 封筒のマナーも重要:表面に「退職届」、裏面に所属と氏名を書き、〆マークで封をします
【最重要】「退職願」と「退職届」決定的違いと使い分け
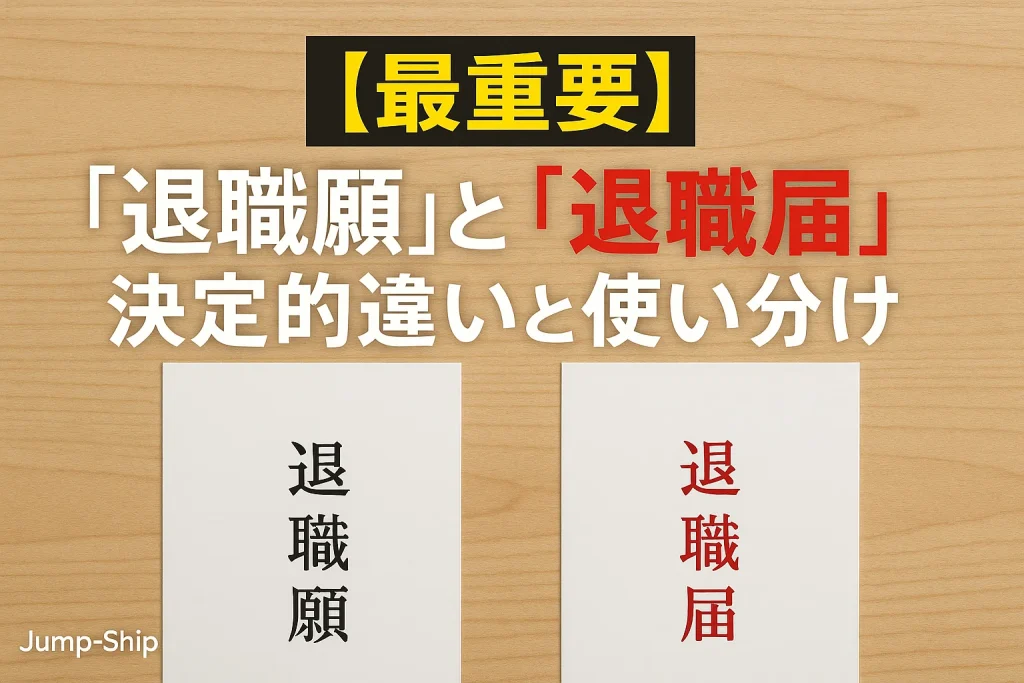
- 退職願:会社に退職を「お願い」する書類(合意前に提出)
- 退職届:会社に退職を「届け出る」書類(合意後に提出)
- 法的効力の違い:願は撤回可能、届は原則撤回不可
- 一般的な流れ:口頭合意→退職届提出が基本パターン
まず、似ているようで全く意味が異なる、この2つの書類の違いを理解しましょう。
| 退職願(たいしょくねがい) | 退職届(たいしょくとどけ) | |
|---|---|---|
| 目的 | 会社に退職を「お願い」する | 会社に退職を「届け出る」 |
| 提出タイミング | 退職の意思を最初に伝える時(上司との合意前) | 退職日が正式に確定した後 |
| 法的効力 | 会社が承諾するまでは、撤回できる可能性がある | 提出され、会社が受理したら、原則として撤回できない |
結論:ほとんどの場合、まずは上司に口頭で退職の意思を伝え、退職日が確定した後に、会社の指示に従って「退職届」を提出する流れになります。
一般的な流れは「口頭で合意 → 退職届を提出」が基本パターンで、退職願は必須ではないケースが多いです。
退職届を出す前の一連の流れは、こちらの記事で完璧に把握できます。
→ [ 【初心者向け】退職手続きの流れと必要書類チェックリスト完全版]
【準備物】書き始める前に用意するものリスト
- 便箋:白無地で罫線が入っていないもの(A4またはB5サイズ)
- 封筒:白無地で郵便番号枠がないもの(A4なら長形3号、B5なら長形4号)
- 筆記用具:黒のボールペンまたは万年筆(消せるボールペンや鉛筆は厳禁)
- 印鑑:認印でOK(シャチハタは避けるのが無難)
準備するものは非常にシンプルです。特別な道具は必要なく、一般的な文具店で手に入るものばかりです。
✅ 便箋
白無地で、罫線(線)が入っていないものを選びます。サイズはA4かB5が一般的です。コクヨなどの文具メーカーから、退職届専用の便箋も販売されていますが、通常の白い便箋で十分です。
✅ 封筒
白無地で、郵便番号枠がないものを選びます。便箋のサイズに合わせ、A4なら長形3号、B5なら長形4号を選びます。
✅ 筆記用具
黒のボールペンまたは万年筆を使用します。消せるボールペンや鉛筆は絶対に使用しないでください。正式な書類のため、消去可能な筆記具は不適切とされています。
✅ 印鑑
認印でOKです。シャチハタは避けるのが無難ですが、会社によっては問題ない場合もあります。不安な場合は、事前に人事部に確認するとよいでしょう。
【テンプレート】コピペOK!そのまま使える退職届
会社の規定が特にない場合は、縦書きがより丁寧な印象を与えます。PC作成の場合は、横書きでも問題ありません。
テンプレート①:縦書き(最も丁寧)
【コピーして使える】
退職届
私儀
この度、一身上の都合により、来たる令和〇年〇月〇日をもちまして、退職いたします。
令和〇年〇月〇日
所属部署名
(例:営業部 営業一課)
氏名 印
会社名
(例:株式会社〇〇)
代表取締役社長 〇〇 〇〇 殿
テンプレート②:横書き(PC作成の場合)
【コピーして使える】
退職届
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇
代表取締役社長 〇〇 〇〇 殿
所属部署名:営業部 営業一課
氏名:〇〇 〇〇 印
私儀
この度、一身上の都合により、来たる令和〇年〇月〇日をもちまして、退職いたします。
以上
これらのテンプレートをコピーして、〇の部分をあなたの情報に置き換えるだけで、正式な退職届が完成します。
【図解】書き方のポイント徹底解説(縦書きの場合)
縦書きの退職届を作成する際の、各部分の詳しい書き方を解説します。正しい配置と内容を理解することで、マナーに沿った完璧な書類が作成できます。
1. 表題
- 一行目の中央に「退職届」と本文より少し大きく書く
- 文字の大きさで重要性を表現
- 退職願の場合は「退職願」と記載
一行目の中央に「退職届」と、本文より少し大きく書きます。これにより書類の性質が一目で分かり、受け取る側にとって分かりやすくなります。
2. 私儀(わたくしぎ)
二行目の最も下に書きます。「私のことで恐縮ですが」という意味の謙譲語です。ビジネス文書における正式な表現で、相手への敬意を示す重要な要素です。
3. 本文
退職理由、退職日を明記します。理由は「一身上の都合により」と書くのが鉄則です。具体的な退職理由を書く必要はありません。むしろ、詳細を書くことで不要なトラブルを招く可能性があります。
4. 提出日
退職届を提出する年月日を書きます。退職日ではなく、書類を提出する日付であることに注意してください。
5. 所属と氏名
部署名を正式名称で書き、自分の氏名をフルネームで記載します。氏名の下に、少し重なるように捺印します。部署名は略称ではなく、正式名称を使用することが重要です。
6. 宛名
会社の正式名称と、代表者の役職・氏名を書きます。敬称は「様」ではなく「殿」を使うのが一般的です。自分の名前より上に書くのがマナーです。
「一身上の都合」と伝える際の、具体的な会話術はこちら。
→ [退職理由の伝え方【例文15選】角が立たない無難な言い方集]
【図解】封筒の書き方・入れ方・渡し方の完全マナー
中身が完璧でも、封筒の扱いで評価を下げてはもったいない。最後のマナーまで徹底しましょう。
封筒の書き方
- 表面:中央に少し大きめの文字で「退職届」とだけ書く(宛名は不要)
- 裏面:左下に自分の所属部署と氏名をフルネームで書く
- 封は必ず〆マークで:のりでしっかりと封をし中央に「〆」を記載
表面:中央に、少し大きめの文字で「退職届」とだけ書きます。宛名は不要です。
裏面:左下に、自分の所属部署と氏名をフルネームで書きます。
便箋の折り方・入れ方
1. 三つ折りにする:下から3分の1を、書き出しが上になるように折り上げます。
2. 上から折り返す:次に、上から3分の1を、折り上げた部分に被せるように折ります。
3. 封筒に入れる:封筒を裏側から見て、便箋の右上が封筒の右上に来るように入れます。こうすることで、受け取った相手が開封した時に、書き出しが最初に見えるようになります。
4. 封をする:のりでしっかりと封をし、中央に「〆」マークを書きます。
渡し方
手渡しが基本です。上司に直接、両手で「よろしくお願いいたします」と一言添えて渡します。
郵送を指定された場合は、この封筒をさらに一回り大きい封筒に入れ、「親展」と朱書きして郵送します。
FAQ(よくある質問)
- 手書きとパソコン、どちらで作成すべきですか?
-
会社の規定がなければ、どちらでも問題ありません。手書きの方が丁寧な印象を与えやすいですが、字に自信がない場合は、読みやすいパソコン作成の方が良いでしょう。署名部分だけ手書きにするという方法も一般的です。
- 退職願の場合は、書き方が変わりますか?
-
はい、少し変わります。表題を「退職願」とし、本文を「~退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」という、お願いする形にします。
- 会社指定のフォーマットがある場合は、それを使うべきですか?
-
はい、必ず会社指定のフォーマットに従ってください。その場合、この記事で紹介したような便箋や封筒は不要で、事務的な書類として提出するだけでOKです。
- 退職届を提出したのに、受け取ってもらえません。
-
直属の上司が受け取らない場合、人事部やさらに上の役職者に提出します。それでも受理されない場合は、内容証明郵便で会社に送付するという最終手段もあります。これは、退職の意思表示をしたという法的な証拠を残すためです。
- パートやアルバイトでも、退職届は必要ですか?
-
就業規則で定められていれば必要です。定めがない場合でも、トラブルを避けるために、簡単なものでも良いので書面で提出しておくのが最も安全で丁寧です。
まとめ:formalities をきちんと済ませ、気持ちよく次へ
退職届は、あなたがその会社で過ごした時間への感謝と、新しい未来への決意を示す、最後の公式な書類です。
一見すると堅苦しいルールが多いように感じますが、一つひとつのマナーには、相手への配慮が込められています。この「最後の仕事」を完璧にこなすことで、あなたは会社との良好な関係を保ち、何より自分自身がスッキリとした気持ちで、新しいスタートを切ることができるのです。
このテンプレートとマナーガイドが、あなたの輝かしい門出の一助となることを願っています。
■ 公式/参考URL一覧
- ハローワーク インターネットサービス – 退職・解雇:
- 退職に伴う公的な手続きの解説の中で、退職の意思表示の重要性について触れられており、退職届がその証拠となることの背景情報として参照。
- doda – 退職届・退職願・辞表の違いと書き方【テンプレートあり】:
- 転職エージェントの視点から、「退職願」と「退職届」の実務的な使い分けや、円満退職に繋がるマナーについて、実践的なノウハウを参照。